こんにちは!ウッチーです 😊
久しぶりの投稿になります。
実はこの数週間、いろんなことが重なってしまい、なかなかブログを書く気持ちになれずにいました。
ようやくひと段落ついた今、少し心の整理もかねて、この間のことを振り返りながら書いてみたいと思います。
実家の片付けと、慌ただしい日々
実家の解体が決まり、やっとその前の片付け作業をはじめました。
着物や食器、カーテンなど「まだ使えそうなもの」は、なんとか自宅へ移動。
個人情報が載っている書類はシュレッダーで処理し、収納をひっくり返して確認、仕分け…。
「残す」と決めたものは自転車で少しずつ運びました。とはいえ、大きくて重たいものはどうしても無理があって。
あと1週間ほどで解体ですが、「もう成り行き任せでいいかな…」と思い始めています。
並行して、地区委員としての活動も続いていました。
分団登校の集合場所で「子どもたちのマナーが心配」という声があり、登校時に立ち会ったり、地区代表に相談してご意見を伺ったり。
いただいたアドバイスを参考に、私なりに考えをまとめて、何度か見守りにも行っていました。
バタバタと動き続けた日々でしたが、実家の片付けを通して、思いがけず母や家族のことを深く思い出す時間になりました。
着物と手編み、母のこだわりに触れる
片付けの中でも、特に印象に残ったのが母の遺した着物や手仕事の品々です。
母は昔から、素材にとてもこだわる人でした。
「そんなに違うの?」と半信半疑だった私ですが、今回の片づけで着物や毛糸に触れてみると、その手ざわりや重み、色合いの深さに、少しずつ母の言っていたことがわかるような気がしてきました。
「着物は半分に減らした」と母は話していましたが、実際には20〜30枚ほどが出てきました。
中には、母が自分で仕立てたと思われるものもありました。
喪服も数着、袖を通さないまま大切にしまわれていて、おそらく花嫁道具として持ってきたものなのだろうと思います。
押し入れの奥からは、大量の毛糸と、母が編んだセーターがいくつも見つかりました。
どれも丁寧な作りで、ほんの少しの余り糸まできれいに残されていて、几帳面な母の性格がそのまま表れているようでした。
民謡と踊りへの情熱
母は踊りがとても好きで、民謡にも強いこだわりがありました。
以前、「民謡の先生の発音、あの土地の訛りと微妙に違うのよ」と熱く語っていたことがありました。
母の生まれは福井。その訛りの違いがわかるなんて、当時は生まれ育った場所だからかなと感じていたのですが、今回、実家の片付けで出てきた大量の民謡のカセットテープやCDを見て、なんとなく納得しました。
母は、踊りをただ楽しんでいたのではなく、
音の違いや地域ごとの文化背景まで、真剣に学び、聴き込んでいたんだと気づいたんです。

母として、そして一人の女性として
母は、私たち子どもを育てるために、何度も仕事を変えてきました。
その事実を、私は母が残した書類を整理する中で初めて知りました。
子どもたちを大学まで通わせるため、母は独学で簿記2級の資格を取り、正社員として事務の仕事に就いたと聞いてはいました。
でも、私たちが大学を卒業した後は、より負担の少ない仕事や、手芸店の店員として働くようになっていったようです。
そのかたわら、手編みのセーターなどを作っては、売れたことを嬉しそうに話していた母の姿を思い出します。
家計を支えるために懸命に働きながらも、母は踊りや手仕事といった「好きなこと」に、いつも誇りをもって向き合っていました。
今回の片づけを通して、私は初めて
「母親としての母」だけでなく、
「一人の人間としての母」の姿を見たような気がします。
ただ物を整理していたつもりが、ふと見つけた手紙に心をふるわせたり、アルバムのページをめくるうちに当時の記憶がよみがえったり……。
気づけば、整理していたのは“物”ではなく、“私自身の心”だったのかもしれません。

最後に
実家の片付けは、想像以上に体力も気力も使いました。
それでも、母の人生のひとコマひとコマを丁寧にたどれたこの時間は、
きっと今の私にとって、意味のあるものだったのだと思います。
全部をきれいに片付けることはできなかったけれど、
焦らず、ゆっくり、自分のペースで。
思い出は、これからも少しずつ大切にしていきたいです。
※この記事は、私のアイデアをもとに、AIの力も借りながらまとめました。
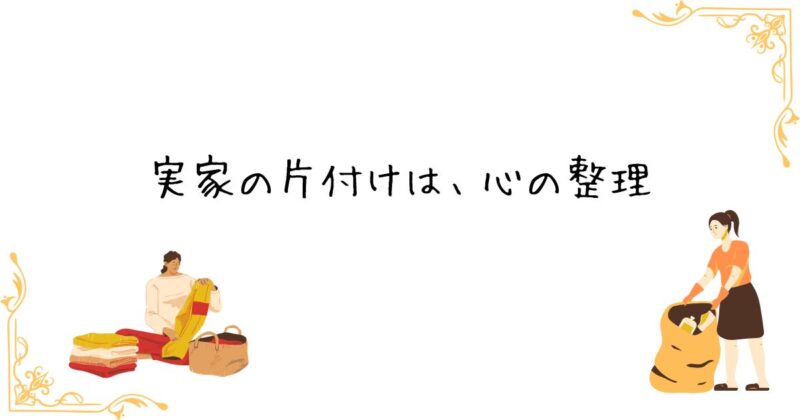


コメント